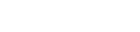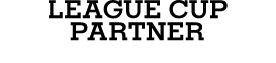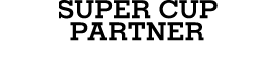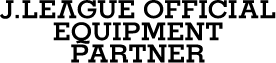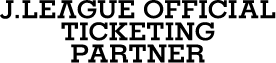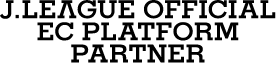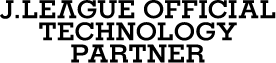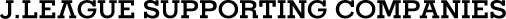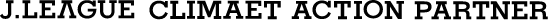SUSTAINABILITY
辻井執行役員インタビュー
~サステナビリティ部の“元年”を振り返る~
2023.12.25
サステナビリティ部の“元年”を振り返る
創設30周年を迎えた2023年にJリーグは、これまでの社会連携活動「シャレン!」を引き継ぐ「社会連携グループ」と気候変動問題に取り組む「気候アクショングループ」を併せ持つ「サステナビリティ部」を新たに設けた。気候変動問題に地域創生を絡めた戦略の構築に乗り出したJリーグの目指すところは何なのか。そのアクションプランをリードする辻井隆行執行役員(サステナビリティ領域担当)に2023年の活動を振り返ってもらった。
地域密着を掲げるJリーグはこれまで、地道にホームタウン活動、そして社会連携(シャレン!)活動に打ち込んできた。現在60を数えるJクラブは、それぞれの所在地を中心に年間2万3000回以上のホームタウン活動を行っている。そのホームタウン活動の中で自治体やNPO(非営利団体)などと三者以上で連携し、少子高齢化など地域が抱える社会課題の解決にトライするのが「シャレン!」である。こちらもJクラブがハブとなって年間2000回以上が行われている。辻井が今、あえて強調するのは、新設された部にとって「シャレン!」と気候変動への取り組み「気候アクション」はクルマの両輪であり、コインの裏表のように密接な関係にあるということだ。
地球温暖化という言葉が地球沸騰化に塗り替わりつつある今、気候変動が誰にとっても重要な関心事であるのは間違いない。人類の存続のために二酸化炭素(CO2)など温室効果ガス(GHG)の削減は「待ったなし」の課題。気候変動で社会の基盤、生活の土台がぐらつくようでは安心してスポーツを楽しむことはできないのだから、発足当初から社会との関わりにこだわりを持つJリーグとJクラブがパートナー企業や団体を募り、一緒にその解決に前のめりになるのはごく自然なことといえる。
では、実際にJリーグは部を新設して何をやろうとしているのか。2022年にJリーグの社外理事に、2023年から執行役員に就いた辻井は「部として何か具体的なことがすごくできたというわけではない。今は土壌づくりを終えて種をまき、少しずつ芽が出始めた段階。もう少し大きく育つのは来年かな、というのが今の感触」と語る。
この1年は自分たちの存在意義や目的、やるべきことをまず部内で整理し、それを基に戦略を立案して、他部と連携しながら協業してくれるパートナー企業やJクラブとの関係を深めた。先方の思いや事情をくみ取り、立てた戦略とのマッチング作業を繰り返しながら辻井が感じたのは「パートナーの皆さんがすごくオープンマインドで、この問題に向き合ってくれている」という手応えだった。気候アクションはそれだけ喫緊の課題であり、人々の関心を喚起するトピックなのだろう。
気候アクションについてのJリーグの基本戦略は公益社団法人として41都道府県に広がる60クラブのパワーを生かすことにある。
「日本全国にまたがるフットボール・ファミリーが、それぞれのホームタウンで気候変動を止めることに貢献すれば、大きなムーブメントになる可能性がある。サステナビリティ部はそういう動きをけん引する役割と、各地域の取り組みを後押しして良い事例が出れば、それを他の地域に展開するお手伝いをする役割がある」
その枠組みの中でまず着手したのが、Jリーグの1200の公式試合で排出されるCO2の量を計測する仕組みをつくり上げることだった。これは昨年の環境省との連携協定2周年イベントで、Jリーグが「全公式試合で排出されるCO2をカーボンオフセットする」と宣言したことを受けたもの。全クラブの協力を得た結果、試合日に排出されるCO2の量が類推値ではあるが、見えてきたという。
GHGの排出量はScope1(事業者自らの活動による直接排出量)、Scope2(他社から供給された電気・熱などを使うことで生じる間接排出)、Scope3(Scope1とScope2以外の間接排出)と3つのカテゴリーに分類される。
それらをJリーグの試合に当てはめると、Scope 3はサポーターや選手が移動する際に使う飛行機や電車などの排出量も含まれるので、算出するのは簡単ではない。Scope 1と2も苦労した。60クラブのほとんどは自治体が所有するスタジアムを使っており、複合施設の中の体育館が同じ日に使われていたりすると、どこまでがスタジアムでどこからが体育館で使った電気代なのか、区別するのは至難の業だった。
それでも苦労を重ねて、スタジアム周辺の飲食売店で使われる燃料やスタジアムで使われる電気代などはある程度、データ化できるようになった。それらの数値が分かってくれば、例えば電気代なら1キロワット当たりのCO2排出量が分かるので、全体像も見えてくる。
「結論として、1200試合のScope 1と2に相当するCO2排出量のうち、70%以上が電気由来であることが分かった」と辻井。Jリーグの気候アクションパートナーとなった再生可能エネルギー事業などを推進する丸紅新電力、ユーラスエナジーホールディングス、日本自然エネルギーから非化石証書やグリーン電力証書の提供を受け、Jリーグ公式試合で使用した電力を実質再生可能エネルギーとすることで、CO2排出量をゼロにできたという。
もう一つの大きなアクションはNTTグループと協業で始めた「TH!NK THE BALL PROJECT™」。ボールは地球の意味も掛けていて、2023年は横浜F・マリノスとギラヴァンツ北九州、ベガルタ仙台がファン・サポーターと共にゴミを減らすとか、地元の野菜を食べるとか、気候変動に対する打ち手になるような行動変容を促すプロジェクトを試験的に実施した。「来年はもう少し規模を大きくして、アクションの中身も精査して行う」と辻井。
菅義偉元総理は2020年10月の所信表明で2050年までにCO2の排出量をゼロにすると演説した。GHGの排出量と吸収量を均衡させ、実質ゼロにするカーボンニュートラルの概念に沿ったものだった。
辻井に言わせると、CO2を出さない発電方法が日本全国津々浦々に行き渡らない限り、CO2が出続けることは避けられない。それに、一度大気中に放出されたCO2は数百年単位で残るから、今すぐ排出量ゼロを実現したとしても温暖化そのものは続く可能性は高い。出てしまったCO2を回収する方法はないのか。辻井は「地球の環境を再生すると、大気から炭素を地球に吸着し固着させることができる」と説く。
「一番分かりやすいのは森です。木々が健康だとCO2を吸収し、葉緑素が光合成してO2だけを大気に戻してくれる。炭素は、豊かな土の中に何億といる微生物に食べられて木々の根っこを通じて土に戻るわけです。同じことは海藻もしてくれる。そういう意味でも自然環境の再生はすごく大事になってくる」
Jリーグのタイトルパートナーになっている明治安田生命保険相互会社は、気候アクションパートナーとして「未来をつむぐ森」というサブタイトルのついた環境保全の取り組みを始めている。森林には景観の保全以上の意味があるのかもしれない。
辻井はまた、カーボンニュートラルを実現するための手段の一つであるCO2を出さない発電は「地域の創生との相性が良い」と語る。それらの発電は自然の力を利用した再生可能エネルギーがほとんど。利用する力は地域の自然環境、風土に応じて変わるのが当たり前で、それぞれの地域が自分たちに合ったものを選択することになる。小規模でも地域で発電し、それをその土地で暮らす人たちが使って経済活動を回せば、地域の中でいろいろな意味での潤いが循環する。日本の各地で進む、畑の上にソーラーパネルを設置し、太陽の光で発電と同時に野菜を育てる「ソーラーシェアリング」は、そうした循環社会の実現に向けた実験なのだそうだ。そうやって地域の足腰が強くなることは、その上によって立つJクラブにもプラスになる話だろう。
サステナビリティ部の“元年”ともいえる2023年の終わりに、辻井は今後の課題を三つ挙げた。「サステナビリティの文脈の中でJリーグが5年後、10年後に向かって何を実現しようとしているのか、そのロードマップをつくること」「それが絵に描いた餅にとどまらないように、ソーラーシェアリングのような具体事例を増やすこと」「最後は発信の部分。今はウェブサイトに気候アクションのページもない状態。2年、3年かけてステークホルダーの方々とのコミュニケーションプランを考えていかないといけない」
「この三つがそろってくると、僕らのやっていることの認知度、解像度はさらに上がるのかなと考えている」
1年365日のうち、試合のある日だけカーボンオフセットしても効果はたかが知れている、という意見はあるだろう。普段のオフィスや日常生活でもCO2は出ているし、意識変容や行動変容をファン・サポーターに訴えて行動に移したところで、それだけでは地球の温暖化は止まらないと。それでも辻井は「各クラブの各地域での取り組みはものすごく大事になってくる」と訴える。
「仮に60のクラブが小さな発電所を60基、設置したとしても、日本のエネルギー総量から比べれば本当に点みたいなもの。でも、これまでの30年の歴史の中でJクラブは自治体や学校、地域の企業、NPO、関係省庁の地方事務所といった組織とすごく良い関係を築いてきた。地域でハブになっているそんなJクラブが新しいモデルを示すことは、インスピレーションの源になる気がするんですね」
「分度器の角度が手元で1度、2度変われば、30年後にその角度はものすごい広がりになっている。そういう違いを生み出すのが僕たちのゴールの一つかなと思っています。いろいろなやり方を見える化し、そんなやり方もありかもねというきっかけをつくり、それを他の地域にも広げていく。それはやがて元気な地域が緩くつながる自律分散型のネットワーク社会をつくることにもつながっていくと信じています」
サッカー・ファミリーが投じる一石が波紋を広げ、全国的なムーブメントになり、社会の構造まで変える。途方もない挑戦かもしれないが、石を投げなければ、波紋すら広がらない。
文:武智幸徳(日本経済新聞社)